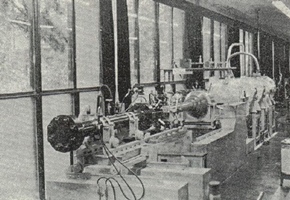次世代太陽系探査
You are here: Home / Future, Solar System Exploration / Impact / Impact Fujiwara
衝突研究から「はやぶさ」,そしてその先へ
Updated : October 31, 2016 - 天体衝突物理
日本惑星科学会誌「遊星人」 Vol. 21, No.2, 2012 掲載
(東大柏キャンパス衝撃波シンポジウム後刷)
藤原顕(2006年3月まで宇宙科学研究所、MUSES-C 計画サイエンスマネージャ)
この原稿元ファイル:[ 日本惑星科学会誌「遊・星・人」第21巻(2012)2号 - PDF ]
要旨
日本の惑星科学における高速度衝突研究の始まりのころ,そしてそれがどのように発展していったか,また探査も含む小惑星の研究にどのように進んでいったか.さらに将来の研究について,「衝突」をキーワードとして述べる.
1. はじめに
この小文を書くに至った経緯を述べておきたい.2012年3 月7 - 9 日に東大柏キャンパスで衝撃波シンポジウムが開かれた.筆者はここで,講演を依頼されて標記のようなテーマで衝突をキーワードとしたこれまでの研究と,これからについて述べた.世話人より,文章に起こして若い人に読んでもらうとよいのではないか,との誘いがあり,少し躊躇したが,まとめておくこととした.レビューでもなく,さりとてまったくの随想でもなく,引用なども厳密さを少々欠いたものであるかもしれないことをはじめにおことわりしておきたい.
2. 高速度衝突実験との出会い
私が京都大学大学院物理に入ったのが,1967年,長谷川博一先生が着任されて宇宙線研究室を開いたばかりであった.翌年は奥田先生も来られ,赤外線天文学も始まったころである.当時研究室では,深海底に堆積した泥の放射性核種 59Ni を定量することによって,泥の担い手となった惑星間空間塵が浴びた宇宙線の永年変化を調べようとしていた.このため泥の採取のため遠洋航海に参加したり,反応断面積を決めるためのサイクロトロンを使った核反応実験の手伝いをしたりもした.またその背景として惑星間塵にも関心がもたれ,とくにその力学を調べる勉強会が持たれることとなった.この勉強会には長谷川先生を中心として向井正,山本哲生,小池千代枝さんら,それに私,のちに浅田智朗君らがいた.私自身は惑星間ダストを地球外でピエゾ素子を用いて直接測定をしようとしていた.その地上での校正用に微粒子を高速度で飛ばすダスト加速器を作ろうとしていた.しかし,それ以前にロケットで上空に滞在中に測定されたと思われたダストのカウントデータは検出器のノイズであることが明らかになった.今考えると,惑星間ダストの空間分布は非常に小さいので,ロケットで検出できないのは当然であるが,そんな時代であった.結局,測定には衛星を使わなければならないということになり当時では実現不可能であった.しかし,小型のダスト加速器がのちに宇宙研に移ってから再製作され,これが柴田裕実さんや長谷川直君らによって東大3MV バンデグラ―フを利用した本格的なダスト静電加速器の運用へと育っていき,さらに野上,大橋,佐々木晶さんらによるダスト測定器の探査機搭載の準備にまでつながっていくこととなった.
一方で,これらの経験を通じて,スペースでの高速度衝突に対する関心が芽生えつつあった.しかし海外では高速度衝突の実験が行われているということを当時の教科書[1] で知るのみであった.挫折感をもっていたころ,たまたま京都新聞に宇宙速度で弾丸を飛ばす装置が京大工学部航空工学に完成したという記事を目にした.いわゆる2 段式軽ガス銃であるが,エネルギー源として火薬を用いたものではなく,高圧圧縮空気を使ったものであった(図1).二段式軽ガス銃としては,国内最初の装置であった.こののち,東工大,東北大など,ショック物性研究用の装置が国内にも作られていくことになる.この実験室(宇治にある超空気力学実験室)はショックチューブを用いて実在気体の衝撃波の物理を調べていたので,それらの応用として開発されたものであった.
図 1. 京都大学航空工学教室長空気力学実験室のバリスチックレンジ.
直接,神元五郎先生に電話を入れて見学に伺ったところ,それなら実験をやってみなさいと快く受け入れてくださった.当時,万年オーバードクターの身でありながら,また学部の壁を越えて受け入れてくださったことにいまでも感謝の念でいっぱいである.聞くところでは,後で長谷川先生が挨拶にいってくださったそうである.これが,本格的な高速度衝突実験との出会いということになった.1975 年ごろのことである.
3. 衝突破壊実験 [2]
この装置で,まず行ったのが小天体にみたてた玄武岩のブロックに高速プラスチック弾丸(7 mm 径)を 3 km / s 程度で衝突させて破壊し,サイズ分布などを調べる実験であった.実は類似の実験はクレーター実験学の大御所である Gault がすでに1969年に行ってはいたが,かれらはテクタイトの起源を説明しようとしていた.このころはまだ,衝突破壊実験に対して惑星科学的な視点がなかったものと思われる.なにしろ,やっとマリナー10号による水星の近接写真(1975)から表面がクレーターで覆われているというようなこと,地球からのレーダー観測で金星の表面にもクレーターがあるらしいというようなことが分かり始めた時期である.またマリナー 9 号(1971)は,フォボスとダイモスをとらえ,はじめて小天体の丸くない姿が明らかになった.このころ同じ物理教室内では林忠四郎先生,中沢さんらを中心として太陽系の起源の理論の構築が行われていた時期であり,惑星集積の素過程を調べる実験という意味合いも持っていた.学会はまだなく,月惑星シンポジウムが発表の場であった.われわれの実験につづいて,東大の松井さんら,名大の水谷仁,高木靖彦,さらに加藤学,荒川さんら,US の Davis,Hartmannら,そしてイタリアでも衝突/衝突破壊実験が始められ次第に実験者が増えた.このような流れの中,Catastrophic Disruption Workshopが,今は亡き Farinella らが提唱して1985年に Pisa で開かれ,私と高木さんが参加した.その後このワークショップは現在にいたるまで不定期に行われている.第 3 回は1990 年に京都で行った.実験によって得られたデータは,破片のサイズ分布,破壊を起こすための Q = E / M(衝突エネルギー E をターゲットの質量Mで割った量,つまりターゲットの単位質量あたりの投入エネルギー),破片のサイズと速度の関係などのほか,高速度撮影を用いた破片の運動の研究へと進められた.
これらを用いた応用研究として,小惑星の族(平山ファミリー)についての研究がある.小惑星の族は1918年に平山清次博士が発見したものである.彼は,木星の重力による摂動分を差し引いた固有軌道要素を共通にする小惑星の集団を発見し,これを族と呼んだ.彼の発見した族は Themis, Eos, Koronis, Flora などで,これらの族はもともとあった母天体が爆発で分裂したものであろうと考えた.その後,古在先生を始めとして族の研究が進められ,また発見される小惑星の数も増えて族に所属する小惑星メンバーの数も多くなった.たとえば Asteroids III によると Themis 族には 500 を上回るメンバーが登録されるまでになっている.とにかく当時はまだ少なかった族に対して衝突実験データを適用しようと考えた.族を構成する小惑星の質量を加え合わすことによって母天体の質量を知ることができる.構成小惑星の軌道長半径の分散から速度分散が分かる(軌道長半径は摂動によって変化しにくい量であるので).これらの情報に衝突実験結果を適用して,どんな衝突が起こったかを推定した.今から見ると稚拙なものであったが,これがきっかけとなって,こののち族を衝突の力学という観点から考える研究が多くなり,今ではこれが当たり前になった.
初期のころは,破壊の程度をあらわす量として(最大破片の質量)/(元の標的物体の質量)が 1 / 2 になるために必要とされる Q 値(前出)は天体の大きさによらず一定とされたが,やがて当然であるが,物体の大きさとともにどのように変わるかという,いわゆるスケーリング則が問題となった.Housen やHolsapple は以前からクレーターに対して次元解析法を用いてこのスケーリング問題を考えていたので,破壊に関してもこの方法を適用して研究を行った.一方,日本でも水谷さんが,いわゆる水谷スケーリングを提唱した.これらのスケーリング則は実験を進めるうえでの実験パラメターの選択のよりどころとなり,指導的役割を果たしてきた.スケーリング則はその後もなお発展と検証が進められるとともに,実験サイドでも破片の速度分布などが中村昭子,小野瀬さんらによっていろいろな条件下にわたって研究が進められている.このような流れの一方で衝突破壊を数値シミューレーションで研究する流れも現れた.最初の本格的な研究は Asphaug であったと思う.物体の強度が支配的になる条件下,および重力が支配的になる領域の現象を調べるコードが開発され,いろいろな天体破壊現象に適用された.1990年代後半には Michel らによる飛散した破片群の間の重力的な干渉も考慮して現象をフォローするような研究も現れた.
すこし時代をさかのぼって小惑星の話にもどる.実験をはじめたころ小惑星に関する文献としては Gehrel が編集した Physical Studies of Minor Planets というペーパーバックの本があった[3].この本は1972年 NASA 出版の論文集録であるが,この時点で,登録されていた小惑星の数はわずかに 1748 個であった.小惑星の形状は変光観測をもとに簡単な推定が行われるといった程度であった.この本の見開きのところに地球型小惑星の一つである Geographos の想像イラストとして,細長い棒の両側に半球がついた人工的なものが掲載されている.この天体は現在ではレーダー観測によって本物に近いモデルが出されている.この本を継承してその後,よく知られている Arizona Univ. Press 出版のAsteroidsシリーズへと引き継がれていく.Asteroids(1979), Asteroids I(I 1989),Asteroids II(I 2002)がそれである[4].
小惑星のラブルパイルモデルという言葉は Asteroid II の中にDavis らが使っている.似たような概念は筆者も衝突破片速度の計測実験から,ある程度大きな破片は速度が遅いので, 衝突破壊後に降りつもるという概念を出していた.1980年の論文ではコンタクトバイナリーの存在を少し述べた.ラブルパイルやバイナリー,コンタクトバイナリーといった概念は今や当たり前として使われている.小惑星も1991年になり,はじめてその姿が直接探査機によって撮像されるようになった(951 Gaspra).243 Ida のように実際に衛星が付随しているようなものも探査で明らかになった.ただ,これらの小惑星はメイン惑星への探査の途中で画像が取られたもので,小惑星そのものをメインターゲットとしたミッションではなかった.小惑星の中でも大きなものは衝突後の破片を再集積したものであろうということで,ラブルパイル構造をもつものが多いであろうというのが,多くの予想であった.一方,小さな小惑星はそうでなく単体(モノリシック)であろうと考えられた.小惑星の自転の分布からもこの考えが支持されていた.ところが実際に探査機から撮られた画像を見るかぎり,Gaspra,Ida,Eros といった大きな小惑星がラブルパイルの様相を呈していないということで,謎とされた.この問題は現在でも解決されたわけではない.
4. 小天体の探査にむけて
1980年代終わりごろになると日本でも惑星探査を始めたいという動きがでてきた.それまでに惑星間空間に向けて打ち上げられた探査機は1985年ハレー彗星に向けての 2 機の探査機「さきがけ」と「すいせい」,1990年に打ち上げられ地球-月間でスイングバイ実験を行った「ひてん」があり,惑星探査後発国ではありながらも着実に技術が蓄積されつつあった.ただこれらの探査機での観測では,まだ本格的に惑星科学者が参加したものではなかった.当時,惑星科学者コミュニティとしては,まず月探査からスタートし火星,水星や小惑星という具合に段階的に進めていこうと考えていたようである.このあたりの経緯については私も十分把握していない.小天体に向けたミッションとしては,このころ考えていたものとして近地球型小惑星のランデブー探査と,彗星をターゲットとした日米共同のサッカーミッションというのがある.
サッカーミッションについては,日本側は上杉,川口,清水先生を中心に,私も研究会に加わることになった.これは彗星に接近し,フライバイの際に彗星から出るダストを捕獲して地球に持ち帰るというものであった.そこで相対速度 km / s オーダーの速度で飛び込んでくる塵を,できるだけ,破壊・変性させずに捕獲するための方法を開発することになった.私たちは門野,中村さんらとともに,すでに京都の実験室に設置していた自前の二段式軽ガス銃を使って発泡スチロールやスタックした薄いシートなどに 4 km / s までの速度で弾丸を打ち込み,どのような現象が起こるか,入射粒子は捕獲できるかどうかといった実験を行うことになった.のちにはエアロジエルという低密度材を用いても行った.しかし,当時ターゲットとしていた彗星と探査機の相対速度 8 km / s では捕獲が不可能であろうということになった.そうこうしているうちに米側は相対速度が 6 km / s という Wild 2 彗星と探査機軌道を見つけ出し,すぐ後で述べるディスカバリープログラムとして結局 Stardust というミッションで実現することとなる(1999年打ち上げ,2006年試料帰還).しかしこのときに調べた低密度体に対する衝突貫入実験の成果は,後に北沢君らによってデブリ捕獲研究に,また Stardust で持ち帰られた試料の解析に関連した実験(奥平さんら)として引き継がれることとなった.さきに述べたが,小惑星探査としてはランデブー計画があったが,これには私はかかわっていない.しかし,これも結局 NEAR 計画としてNASAが取り上げ,Eros を探査することとなった(1996年打ち上げ,2000年ランデブー).これは小惑星を主ターゲットとした初めてのミッションとなった.
私が宇宙研に移ったのが1992年の秋,この年ちょうど日本惑星学会の立ち上げが京都であった.この学会成立の一つの大きな動機づけとして日本の惑星探査をエンカレッジするというものであった.宇宙研に移ってすぐ上杉,川口先生と US で開かれたディスカバリープログラムのミッション選択の公開シンポジウムに参加した.全米の研究機関から 70 を超す惑星探査ミッション提案があり,米国の惑星探査に関係するグループの層の厚さの日本のレベルとの差をまざまざと見せつけられた.私も宇宙研に移る前ごろから,小惑星探査をどのよう行うべきかに目が向いていた.1985年には小惑星サンプルリターンについての研究会が鶴田先生の呼びかけで宇宙研で行われ,そこで族小惑星のメンバーをつぎつぎに探査していって母天体の復元をしようという提案を行った.また,小惑星フライバイに際して第 2 体を衝突させて舞い上がった塵を探査機がキャッチして地球に持ち帰るという方法を月惑星シンポジウムで提案した(1990年).しかし,当時これらを惑星科学者が現実的な計画に作り上げるのには力量不足であった.
これに似たミッションがのちに NASA で Tempel1 彗星をターゲットに DEEPIMPACT ミッションとして行われている(2005年打ち上げ).もっとも,このミッションではダストを捕獲するのではなく衝突時の発光を観測するというものであったが.このような状況の中で,われわれとしてどのようなミッションを行うべきか,ということになった.いろいろな経緯はともかく,結論として小惑星サンプルリターンを行おうということになった.サンプルリターンは惑星探査としては最もレベルの高い技術を必要とする.最初からサンプルリターンによってサイエンスを目的とするより,むしろ,工学実験探査機と位置付けて,今後本格的なサンプルリターンを行うための基本技術を習得することを目的とするものであった.われわれ探査を行いたい惑星科学者にとって幸運であったのは工学の人たちがこのような難度の高いミッションに対して非常に意欲的であったことである.もちろんこのような野心的なミッションをエンカレッジした宇宙研上層部の理解と熱意がなければ進めることができなかったであろう.MUSES-C(はやぶさ)の詳細について,ここで詳細をあれこれと話すつもりはない.この小文では衝突というキーワードで話しているのだから.
ともかく,サンプルリターンを行うということになり,試料の採取法を考えるグループを国内の理学工学の研究者とメーカーに参加してもらい立ち上げた.いろいろとブレインストーミングの結果,衝突で舞い上がった試料を採取するということになり,これまで行ってきた衝突の研究が生かされることとなった(というよりこれまでの研究をバックにしてこのような採取法が組み立てられたといったほうがよい).この方式のポイントは,小惑星のような低重力下では弾丸の衝突によって初速が与えられた放出物はその速度を維持したままで上方に向かうので,それをスカート状のホーンで集めて狭い収納箱に導くという点である.安部,長谷川,矢野,高木君らと実験室で衝突実験をくりかえし,また航空機や落下による無重力試験を行い,試料の収率や変成を抑えるといったことを考えて衝突条件が決定された.発射器の開発は東北大高山研究室に世話になり,厳しい環境下で確実に動作するものにするための機構の開発,また材料の選択などを大学の理学工学にまたがる研究者,メーカーとの共同で行なった.しかし探査機に組み込まれた最終的なものはホーンの入り口が狭くなったり,いろいろな制約を受けたのは少し残念であった.サンプラーは本来予定したとおりには作動できなかったが,帰還した容器に微小なものではあったものの試料が見つかってほっとした.
さて,はやぶさが探査した小惑星イトカワであるが,あらかじめ想像していたものとはかなりちがったものであった(探査機が到着する前にイトカワがどんな天体かを予想する国内研究会と国際研究会を持ったのだが)[5].本稿のテーマに関連して興味深いのは,イトカワがラブルパイルであろうということである.これは,密度が 1.9 g / cc と低いこと,表面にリッジなどの線状構造が見られないこと,角ばっておらず,丸っこい形をしていることなどから推論された.先にも述べたように,大きな小惑星はラブルパイルであろうと予想されていたが,これまでの探査で見つからず,イトカワのようなちっぽけな天体がラブルパイル構造であるという発見はこの業界で予想外のこととして受け取られた.ほぼ時を同じくして,Michelらは破壊後の破片集団の中で相互の集積がおこり小さなラブルパイル天体ができあがることを数値シミュレーションで示した.しかし,どのような天体がどのくらいの比率でラブルパイルなのかなど,太陽系のグローバルな進化の中でイトカワがどういう履歴をたどって今日に至ったのかという見解はまだできあがっていない.今後,持ち帰られた試料の分析の中からもヒントが得られるかもしれない.
5. 将来
はやぶさを計画したとき理学的目的としてのうたい文句は,「代表的スペクトルタイプに対応する小惑星の物質種や隕石種の決定」であった.はやぶさの探査したイトカワのスペクトルタイプはS 型であった.今2014年打ち上げをめざして準備が進められている「はやぶさ 2」はC 型小惑星をめざすことになっており,当初のシナリオにそって進められている.今回は第 2 の物体を表面に打ち込んで人工クレーターをつくり,内部を露出させた周辺に行って中から露出した試料を採取することも予定されている.C型小惑星がもつ有機物に対する興味とともに,この天体の構造に関する手掛かりも得られそうで,期待をもって見守っている.さらにソーラー電力セイルを利用したトロヤ群探査なども考えられており実現が望まれる.
衝突にかかわってきた者ならば自然界での大規模天体衝突の現場を見てみたいと思うだろう.これにたいして最近,破壊したばかりの小惑星が観測されて話題になった.
ひとつは 2010 A2 という大きさが 150 m 程度の天体である(図 2)[6].これはLINEAR地上観測によって2010年1月6日に発見された. その後 HUBBLE と ROSETTA によって観測された.近日点,遠日点はそれぞれ 2.00 AU, 2.57 AU.発見当初は彗星と考えられたが衝突をうけて破片が散らばったものと考えたほうがよく説明できることがわかった.衝突が起こったのは2009年3月下旬と推定されている.1 億年以上前にできたとされるフローラ族に属している.この天体は,かなり大規模なトータル破壊を起こしているように見られ,おびただしい数の破片群がみられる.もうひとつの天体は 596 Scheila である[7].近日点,遠日点がそれぞれ 2.44 AU,3.41 AU で D 型ではないかといわれている.こちらは直径 113 km と大きく,2010年12月2-3日に衝突したと考えられている.部分的に破壊を起こし,破片が周囲に散らばっているようにみえる.
図 2. 2010 A2.(NASA)
カメラや,いろいろなサイズの試料を捕獲するための装置,あるいはダスト検出器などを搭載した探査機をこれらに接近させて探査を行うというのは面白いと思われる.地球から,ダイレクトに探査機を送った場合,それぞれの天体への接近相対速度は 5.1 km / s,6.1 km / s 程度であるから,なんとかインタクトに近い状態でダストのフライバイ捕獲ができよう.ただし,衝突に対する機器の十分な防御対策が必要である.大きな試料の捕獲や詳細な接近観測には減速したり衝突回避の工夫が必要である.さきに述べた古いファミリーに属する小惑星メンバーをつぎつぎに訪ねて行く探査は困難だが,ここで述べた最近できたばかりのミニファミリーならそのような探査は行いやすく,このような探査によって小天体の内部を直接見るということが現実に可能である.このような研究はアカデミックな意義だけでなく,次に述べるスペースガードの観点からも興味がもたれる.
昨年 2011年11月8日,月までの距離の 5 分の 4 のところをサイズ約 400 m の天体YU55が通過したというニュースが話題になった.100 m 程度の天体が地球に衝突する割合は1000年に 1 回ぐらいと考えられている.規模としてはツングースカのイベントを上回るものとなるといわれる.東日本大震災程度の災害が1000年に 1 度といわれているがそれと同程度の確率ということで無視できないものとなる.もっとも小惑星にたいする確率は地球あたりの確率であるが.さらに規模の大きいものは確率は小さいけれども過去に起こり,全地球的な影響があったことがわかっている.この種の議論で注意すべきことは確率論で片づけてはならないところである.確率の考えはわれわれの知識が不十分で現象の予測が不可能な場合につかわれる概念である.確率だけで考えていると「予想外」ということになって取り返しがつかないことになる.今の場合は危険なサイズの小惑星が十分リストアップされ精度よく軌道がわかり,なおかつ精度の高い計算によって衝突予測が原理的に可能になるであろうことである.もしこれで危険な衝突が確実となった場合,衝突回避を考える必要がある.この意味で小惑星のサーベイと衝突予測の高精度化が重要である.サーベイに関して言えば,かつて磯部琇三さんは昼間に太陽側からやってくるものが観測にかからないと述べていた.これに関して NASA では金星軌道付近にサーベイ用探査機を打ち上げるということも検討されているという報告がされている[8].重大な衝突が確実とわかった場合,衝突回避の手段が必要である.そのためにはまず相手の性質を知る必要があるが,「「はやぶさ」や「はやぶさ 2」,US の OSIRIS Rex,ESA が計画している「ドンキホーテ」など,今後の近地球型小惑星探査は小惑星の組成や構造に関して重要な知識を提供することになろう.さらに,なんらかの危険回避対策のため地球からの緊急発進をして短時間に対称天体に接近するには強力な非慣性飛行のできる強力な推進機を積んだ探査機が必要となろう.
一方で,このような非慣性飛行が可能な探査機は太陽系内の科学探査のスピードを格段にアップさせることができ,惑星科学者のこれへの期待は大きい.おりしも最近 NASA は小型の原子炉を搭載した探査機プロメテウス計画検討の予算を少額ではあるが復活させたというニュースが流れていた[9].かねがね,太陽系探査も重力による慣性航行をメインにしたものから抜け出すべきだと考えているが,そろそろこのようなものを本気で検討する時代にはいってきたように思われる.原子力エネルギーの利用は昨今問題が多いのだが,今の段階で利用できるものはこれにかぎられる.さらに他の未来型の推進機関もいろいろと視野に入れながら,惑星科学者は先の世界と技術も見据えて進む道を提言していきたいと思う.
参考文献
[1] Kinslow, R.,1970, High-velocity impact phenomena (Academic press).
[2] 衝突破壊研究の流れを知るには以下をみよ.Fujiwara, A. et al., 1989, in Asteroids II, 240, 及び Holsapple, K. et al., 2002, in Asteroids III, 443. これらの reference も参照.
[3] http://archive.org/details/physicalstudieso00gehr
[4] 小惑星研究については以下を見よ.いずれも Arizona University Press 発行 Gehrels, T. ed., 1979, Asteroids, Binzel, R. et al. eds., 1989, Asteroids II, Bottke, Jr. et al. eds., 2002, Asteroids III.
[5] はやぶさの観測したイトカワに関してはつぎの特集号をみよ.Science 2-June 2006 (Vol.312, No.5778).
[6] Snodgrass, C. et al., 2010, Nature 467, 814.
[7] Ishiguro, M. et al., 2011, ApJ 741, L24..
[8] NASA panel weights asteroid danger, 2010, Nature 467, 140.
[9] Fission power back on NASA’s agenda, 2012, Nature 482, 141.
” HTML 編集 - ウェブ編集室 ”
You are here: Home / Future, Solar System Exploration / Impact / Impact Fujiwara
CATEGORY: 次世代太陽系探査
... ...
Creating a better future by exploring other worlds and understanding our own.